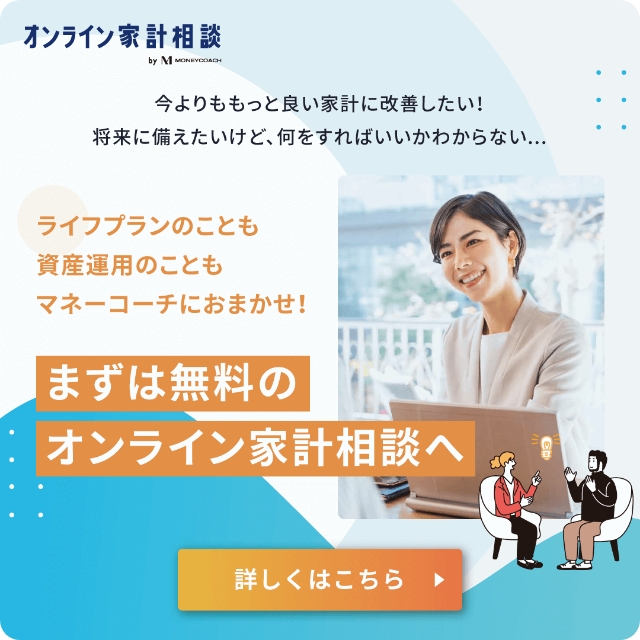家計管理のために家計簿をつけていると、「一般的な生活費はいくらだろう?」と気になる人もいるでしょう。お金のことは周囲に聞きづらいため、現状の生活費が平均と比べてどうか把握することが難しく、中には無駄な支出を重ねているご家庭もあるかもしれません。
本記事では夫婦の生活費の平均額や、世帯主の年齢や居住地域といった生活費に差が生じる要因についても併せて解説します。
理想の生活費は世帯ごとに異なりますが、小さな工夫を取り入れることで生活費を抑えることができます。夫婦2人の生活費を考える際にぜひ参考にしてください。
CONTENTS
夫婦の生活費の内訳
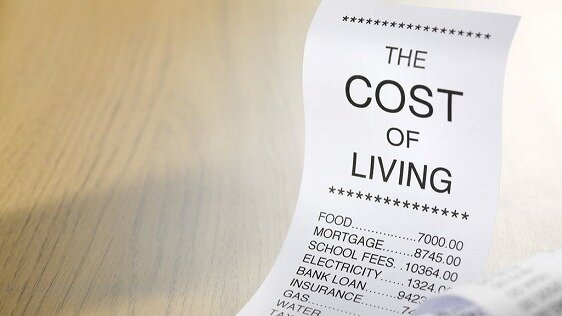
生活費とは、暮らしていくために必要な費用のことを言い、食費や住居費、光熱費などが該当します。家賃はほとんどの場合一定しているため管理が簡単ですが、光熱費や食費は変動するため、月によってはこれらの支出額が増えることもあるでしょう。
では、夫婦の生活費の平均額はどれくらいでしょうか。夫婦2人以上の世帯における生活費の内訳は以下の通りです。
| 支出項目 | 支出金額 | 支出に占める割合 |
| 食料 | 76,440円 | 27.5% |
| 住居 | 17,365円 | 6.2% |
| 光熱・水道 | 21,836円 | 7.8% |
| 家具・家事用品 | 12,538円 | 4.5% |
| 被服および履物 | 8,799円 | 3.1% |
| 保健医療 | 14,211円 | 5.1% |
| 交通・通信 | 39,910円 | 14.3% |
| 教育 | 10,290円 | 3.7% |
| 教育娯楽 | 24,285円 | 8.7% |
| その他の消費支出 | 52,251円 | 18.8% |
| 消費支出合計 | 277,926円 | - |
参考:e-Stat「家計調査(2020年) 家計収支編 二人以上の世帯」より作成
支出項目のうち、特に住居費は「もっと必要なのではないか」と感じる人が多いでしょう。上記の統計は、家賃の支払いがない世帯も含まれているため、賃貸などで家賃の支払いがある世帯にとっては、実際の支出額はもう少し多いことが一般的です。
生活費の平均額を参考にする場合は、単に各項目の支出額に注目するのではなく、支出額に占める割合を確認することも大切です。「夫婦2人以上の世帯」といっても、子どもの有無やライフスタイルによって生活費の内訳は大きく異なるためです。
あくまでも平均値として上記の表を確認し、家計を振り返るきっかけにすると良いでしょう。
生活費に差が出る主な要因
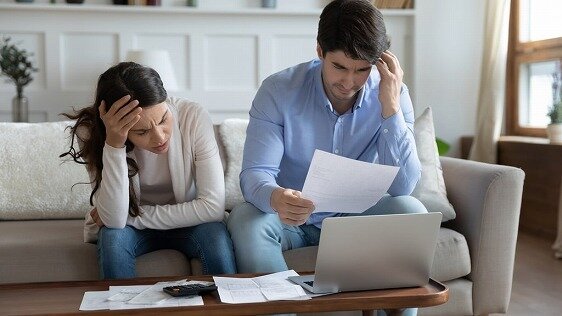
生活費は家族構成やライフスタイルによって差が生じます。また、都市部かそれ以外の地域かといった居住地域も、生活費の総額を左右する大きな要因といえます。
ここでは、生活費に大きな差が出る主要な3項目を確認しましょう。
- 居住地域
- 年齢
- 勤労状況
①居住地域
毎月の生活費は居住する地域によっても差が生じます。地域ごとの消費支出額は以下の通りです。
| 地域 | 消費支出額 |
| 全国平均 | 277,926円 |
| 北海道地方 | 267,187円 |
| 東北地方 | 262,275円 |
| 関東地方 | 293,290円 |
| 北陸地方 | 283,503円 |
| 東海地方 | 281,535円 |
| 近畿地方 | 263,899円 |
| 中国地方 | 272,385円 |
| 四国地方 | 258,476円 |
| 九州地方 | 269,515円 |
| 沖縄地方 | 206,758円 |
参考:e-Stat「家計調査(2020年) 家計収支編 都市階級・地方・都道府県庁所在市別1世帯当たり1か月間」より作成
東京を含む関東地方の支出額と沖縄地方の支出額では8万円以上の開きがあることがわかります。また、住宅費は都市部の方が高く、地方は安い反面、自動車等の利用が多いなど生活費の内訳も異なります。
②年齢
夫婦2人以上の世帯でも、若年層と高齢者層では生活費の支出額が異なります。以下の表は、世帯主の年齢ごとの消費支出額を表しています。
| 世帯主の年齢 | 消費支出額 |
| 全年齢階級平均 | 277,926円 |
| ~34歳 | 261,996円 |
| 35歳~39歳 | 268,725円 |
| 40歳~44歳 | 297,074円 |
| 45歳~49歳 | 333,865円 |
| 50歳~54歳 | 337,847円 |
| 55歳~59歳 | 321,698円 |
| 60歳~64歳 | 293,170円 |
| 65歳~69歳 | 274,798円 |
| 70歳~74歳 | 246,656円 |
| 75歳~79歳 | 230,977円 |
| 80~84歳 | 208,996円 |
| 85歳~ | 200,413円 |
参考:e-Stat 「家計調査(2020年) 家計収支編 世帯主の年齢階級別1世帯当たり1か月間の収入と支出」より作成
子供が生まれる20代後半から40代にかけて支出額が増加し、子供の多くが高校生や大学生を迎える40代後半から50代半ばにかけて、教育費や食費がかさむことで支出額がさらに多くなることがわかります。
また、60代以降の年代では子供の独立や退職などを迎え、消費支出が徐々に減少しています。老後は年金を中心とした生活になる人も多いため、上記の金額を目安とすると良いでしょう。
③勤労状況
生活費に差が生じる3つ目の要因として、勤労状況があります。世帯内で働いている人数が多いほど可処分所得は増えるため、世帯内で何人働いているかによって支出平均額にも、以下のような差が生じます。
| 世帯内の有業者数 | 消費支出額 |
| 平均 | 277,926円 |
| 有業者0人 | 225,166円 |
| 有業者1人 | 272,369円 |
| 有業者2人 | 307,429円 |
参考:e-Stat 「家計調査(2020年) 家計収支編 有業人員別1世帯あたり1か月間の収入と支出」より作成
同一世帯において、働いている人数が多いほど消費支出額も多いことがわかります。夫婦それぞれが働くことで、支出・貯蓄それぞれにまわすお金が増えるため、よりゆとりある生活を送ることが可能です。
ポイントは家計管理!生活費をできるだけ抑えるコツ
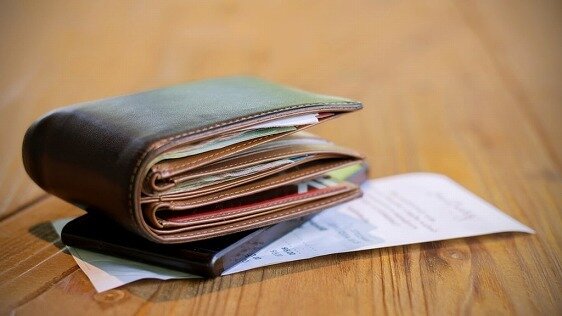
理想の生活費は家族構成や居住地、勤労状況によってさまざまですが、多くの人が生活費をできるだけ抑えたいと考えていることでしょう。
生活費を無理なく抑えるためには、家計をしっかりと見直すことが大切です。ここでは生活費抑制のために実践したい4つのコツを解説します。
- 家計管理方法を見直す
- 夫婦の生活リズムを揃える
- キャッシュレス決済を利用する
- シェアサービスを利用する
①家計管理方法を見直す
共働き世帯が増える中、どのように家計を管理すべきかと悩む人もいるでしょう。無駄な支出をできるだけ減らし、貯蓄割合を高めるためには家計の管理方法が非常に重要です。以下で、家計管理方法を2つご紹介します。財布を1つにまとめる
夫婦の財布を1つにまとめることで、収支が非常に管理しやすくなるというメリットがあります。どちらか一方の収入を生活費に充て、もう一方の収入を全額貯蓄するという方法が一般的です。
また、共通の口座にそれぞれが生活費を振り込み、この口座を通してやりくりすると不公平感が少なく、夫婦で家計を管理している意識が芽生えるというメリットがあります。財布を2つに分ける
例えば、夫が家賃と保育料、妻が食費と光熱費を負担するように、項目ごとに負担者を分けるという方法も多くの世帯で取り入れられています。
収入に応じて負担割合を決められるというメリットがある反面、残りのお金はそれぞれのお小遣いになるため、互いの貯蓄状況がわかりにくいというデメリットがあります。
財布を2つに分ける場合は、定期的にそれぞれの貯蓄を確認する機会を設け、収支バランスを確認しましょう。
②夫婦の生活リズムを揃える
夫婦の生活リズムが違うと光熱費や水道費がかさみがちです。例えば入浴時間が大きく違う場合、浴槽のお湯を温め直すことで光熱費が余計にかさみます。
入浴や食事、起床・就寝時間を合わせるだけでも光熱費を抑えることができます。
③キャッシュレス決済を利用する
クレジットカードやスマートフォン決済が徐々に主流となり、これらの決済方法を利用することで各社のポイントや還元サービスを利用できます。現金よりもお得に買い物ができることがあるため、積極的にキャッシュレス決済を取り入れましょう。
また、例えばクレジットカードの場合、利用履歴をそのまま家計簿の代わりに使うことができ、家計管理に役立ちます。
煩わしくて家計簿はつけていないという人でも、キャッシュレス決済の利用履歴を適宜確認し、収支を把握しましょう。
④シェアサービスを利用する
個人で物を所有せず、さまざまな人と物を共有するのがシェアサービスです。最近では、漫画やおもちゃ、洋服など幅広いジャンルのものをシェアするサービスが出てきています。シェアする対象は様々ですが、いずれも一定期間の利用を前提としています。
特に家具や車などは維持するにも処分するにもお金がかかるため、シェアサービスで代用できないか検討するのも良いでしょう。
まとめ:生活費は地域や年齢で差が出る!上手なやりくりを心がけよう
本記事では夫婦の生活費の平均額を解説しました。平均額にはさまざまな世帯の状況が盛り込まれているため、「平均よりも生活費が多い」と慌てず、あくまでも参考程度に捉えることが大切です。
平均額を踏まえ、「夫婦の生活時間を合わせることはできないだろうか」「シェアリングサービスで代用できないか」など、さまざまな視点から家計見直しを実践してみてください。
理想の生活費を実現するために、家計の項目ごとに無駄のないやりくりを心がけましょう。