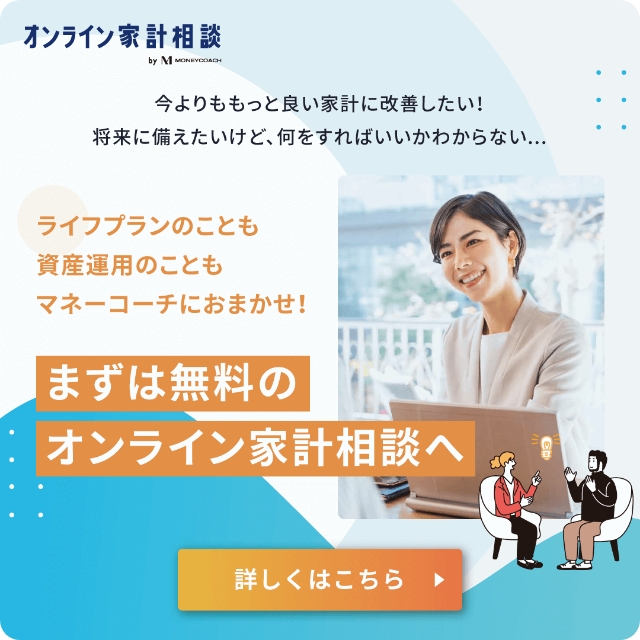日本の労働者の平均的な手取り給与は、おおよそ25万円です。平均的な手取り金額をもらっていても、「結婚したり子どもができたりしても生活できるかな?」「マイホームを持つことは可能?」「老後は大丈夫だろうか?」などの疑問や不安を感じている人もいるでしょう。
この記事では、手取り25万円で生活していけるかについて解説しています。手取り25万の額面給与や年収、生活レベルも紹介するので、将来の家計について考えるきっかけにして下さい。
CONTENTS
手取り25万円の人の額面給与と年収
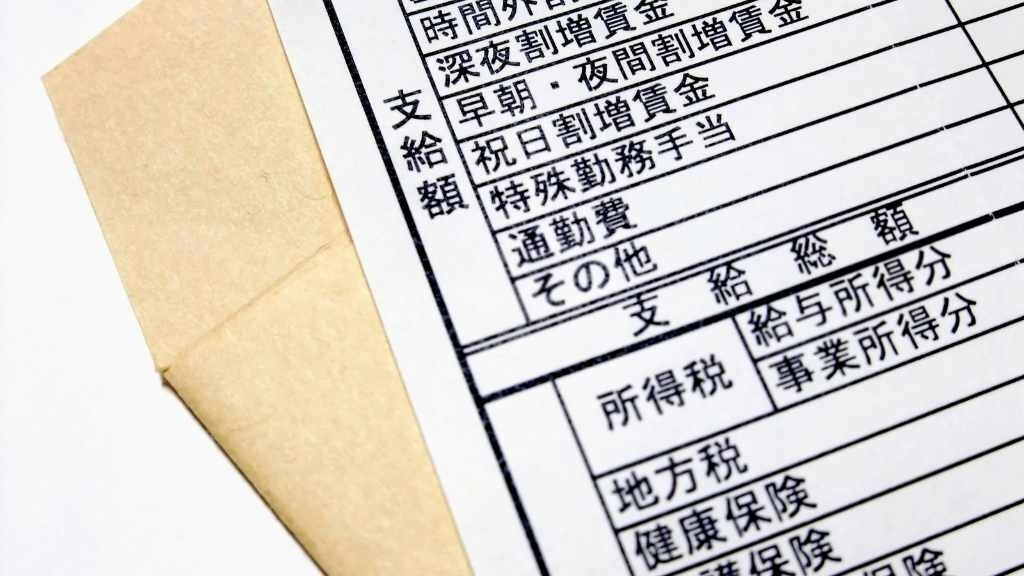
手取り25万円での生活を解説する前に、手取り金額と額面給与・年収との関係を確認しておきましょう。
手取り25万円の人の額面給与は約32万円
手取り給与は家族構成などによって異なりますが、額面給与の約80%です。
- 手取り給与≒額面給与×80%
この式に当てはめると、手取り25万円をもらうには、額面給与は約32万円必要になります。手取り給与が少なくなるのは、額面給与から税金や社会保険料が差し引かれるからです。
税金や社会保険料(労使折半後の労働者負担分)は、次の通りです。
- 所得税:10%(累進課税。所得330万円未満の場合。令和19年までは復興特別所得税が2.1%上乗せとなる)
- 住民税:前年度所得の約10%(地方自治体によって異なる)
- 健康保険料:標準報酬月額(※)の約5%(加入する健康保険組合によって異なる)
- 介護保険料:標準報酬月額の0.82%(2022年3月~、40歳以上の人のみ)
- 厚生年金保険料:標準報酬月額の9.15%
- 雇用保険料:給与の約0.5%(2022年10月~。一般の事業は0.5%。農林水産業・清酒製造業・建設業は0.6%)
※社会保険料や年金額を計算するために、4~6月の報酬を基に算出した金額です。
大雑把にいうと、税金は額面給与の約5%、社会保険料は約15%になります。所得税率などから税金が額面の5%は少ないと感じるかもしれませんが、各種所得控除があるため課税対象額は額面よりかなり少なくなります。
手取り25万円の人の年収は380万円プラス賞与
手取り25万円(額面32万円と仮定)の人の年収は、賞与がなければ約380万円(=32万円×12ヶ月)です。賞与のある人の年収は、約380万円に賞与をプラスすれば計算できます。
国税庁の「民間給与実態統計調査結果」によると、2020年の給与所得者の年収は433万円(男性532万円、女性293万円)で、その内訳は次の通りです。
- 給与:369万円(男性449万円、女性254万円)
- 賞与:65万円(男性83万円、女性39万円)
毎月の手取りが25万円(額面約32万円)で賞与が額面の2ヶ月分の人の年収は、給与所得者の平均とほぼ同額になります。
参考:国税庁「民間給与実態統計調査結果」(以下、同様)
手取り25万円をもらえる人は?|年齢別・業種別の年収

実際に手取り25万円をもらっている人の年齢や業種を紹介します。
平均年収が400万円を超えるのは30代から
前述の国税庁調査によると、年齢別の平均年収は次の通りです。
年齢別の平均年収:
| 年齢 | 平均年収 | 年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 20歳以上25歳未満 | 260万円 | 45歳以上50歳未満 | 498万円 |
| 25歳以上30歳未満 | 362万円 | 50歳以上55歳未満 | 514万円 |
| 30歳以上35歳未満 | 400万円 | 55歳以上60歳未満 | 518万円 |
| 35歳以上40歳未満 | 437万円 | 60歳以上65歳未満 | 415万円 |
| 40歳以上45歳未満 | 470万円 | 65歳以上70歳未満 | 332万円 |
賞与によって異なりますが、手取り25万円の人の年収を400万と仮定すると、30歳以上35歳未満くらいから手取りが25万円を超えることになります。また、35歳以上40歳未満になると、給与所得者の平均年収とほぼ同額になります。
業種別の平均年収は約430万円
国税庁調査によると、業種別の平均年収(年収400万円以上)は次の通りです。
業種別の平均年収:
| 業種 | 平均年収 | 業種 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 715万円 | 製造業 | 501万円 |
| 金融・保険業 | 630万円 | 複合サービス事業 | 452万円 |
| 情報通信業 | 611万円 | 運輸業・郵便業 | 444万円 |
| 建設業 | 509万円 | 不動産業・物品賃貸業 | 423万円 |
| 学術研究,専門・技術サービス、教育,学習支援業 | 503万円 | 全業種平均 | 433万円 |
全業種の平均年収は433万円で、半分以上の業種で平均年収が400万円を上回っています。平均年収400万円台の業種に手取り25万円の人が多いと仮定すると、該当する業種は「複合サービス事業」「運輸業・郵便業」「不動産業・物品賃貸業」です。
一人暮らしで手取り25万円ならばゆとりある生活ができる

一人暮らしで手取り25万円ならば、ゆとりある生活ができるでしょう。生活費の内訳とゆとり具合をみてみましょう。
一人暮らしの生活費の内訳
一人暮らしの人(勤労世帯)の生活費は平均約17万円です。内訳は次の通りです。
一人暮らしの平均生活費・2021年度:
| 生活費 | 費用 |
|---|---|
| 食料 | 3万9,884円 |
| 住居 | 2万9,637円 |
| 光熱・水道 | 1万0,225円 |
| 家具等 | 6,151円 |
| 被服など | 5,932円 |
| 保健医療 | 6,540円 |
| 交通・通信 | 2万3,734円 |
| 教育 | 14円 |
| 教養娯楽 | 1万9,710円 |
| その他 | 2万9,988円 |
| 合計 | 17万1,816円 |
参考:総務省統計局「家計調査 家計収支編 1世帯当たり1か月間の収入と支出(単身世帯)表番号1(2021年)」
住居費の平均金額は約3万円ですが、持ち家の人も含まれるため賃貸の場合は5~6万円以上かかるケースも考えられます。家賃によっては生活費が20万円前後になる場合もあるでしょう。
手取り25万円ならば5万円以上の余裕がある
一人暮らしの平均生活費から考えると、手取り25万円ならば5万円以上の余裕があるといえます。しっかりと貯蓄して、結婚やマイホーム取得などに備えることも可能です。
また、余裕資金を趣味やレジャー、自己研鑽に充てて生活を充実させるという選択肢もあります。どちらを選ぶかは個人の自由ですが、生活充実派の人も将来を見据えて一定金額は貯蓄するのがおすすめです。
家族がいると手取り25万円では生活が厳しい

結婚して家族がいる場合、手取り25万円では生活が厳しい可能性もあります。家族がいる場合の生活費と生活レベルをみてみましょう。
世帯人数別の生活費
家族のいる人(勤労世帯)の生活費は平均約30万円です。内訳は次の通りです。
世帯人数別の平均生活費・2021年度:
| 生活費 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 6万7,170円 | 7万6,289円 | 8万6,019円 |
| 住居 | 2万4,273円 | 2万0,291円 | 1万7,432円 |
| 光熱・水道 | 1万8,476円 | 2万1,344円 | 2万2,773円 |
| 家具等 | 1万1,829円 | 1万2,455円 | 1万3,347円 |
| 被服など | 7,955円 | 9,959円 | 1万2,454円 |
| 保健医療 | 1万3,452円 | 1万3,815円 | 1万2,824円 |
| 交通・通信 | 4万8,715円 | 4万9,899円 | 4万9,962円 |
| 教育 | 1,023円 | 1万6,872円 | 3万2,931円 |
| 教養娯楽 | 2万3,424円 | 2万6,446円 | 3万0,713円 |
| その他 | 6万6,492円 | 5万8,361円 | 5万0,546円 |
| 合計 | 28万2,807円 | 30万5,731円 | 32万8,999円 |
参考:総務省統計局「家計調査 家計収支編 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(表番号3ー1)(2021年)」
手取り給与が25万円ならば、平均的な生活をするには約5万円不足します。節約するなどの対策が必要です。また、マイホームの購入や貯蓄は難しいかもしれません。
毎月の不足分を賞与で補うこともありますが、将来のために少しでも貯蓄するには節約して生活費を抑えることが大切です。
家族が増えると生活はより厳しくなる
世帯人数別の平均生活費より、家族数が増えるほど生活費がかかることがわかります。子どもが2人いて手取り25万円、生活費が33万円ならば、毎月8万円の赤字です。
一般的に進学とともに教育費の負担は重くなるため、赤字を解消するための対策を取らないと子供が独立するまで生活費は年々苦しくなるでしょう。
手取り25万円ならば結婚後は共働きがスタンダード

家族がいると手取り25万円では生活が厳しいですが、共働きならば生活は安定します。共働き世帯の状況について解説します。
結婚後は共働き世帯が約67%
総務省の調査(2021年度)によると、結婚後の夫婦の就労状況(夫が就労している場合)と世帯月収は次の通りです。
- 夫婦共働き(67%):約68万円
- 夫のみ就労(33%):約55万円
夫婦共働きの世帯が67%を占めており、結婚後は共働きが一般的と言っていいでしょう。また、夫のみ就労世帯の平均月収(約55万円)より、妻が専業主婦の家庭は、総じて夫が高収入であることがわかります。
参考:総務省統計局「家計調査 家計収支編 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(表番号3ー11)(2021年)」
共働きならマイホームの購入や貯蓄も可能
共働き世帯の手取りを平均月収の8割と仮定すると、共働き世帯の毎月の収入は約54万円になります。毎月の生活費が30万円の場合、20万円以上の余裕ができる計算です。
生活費にはローンの支払いなどは含まれませんが、月に20万円以上の余裕資金があればマイホームの購入や教育費・老後資金のための貯蓄も十分可能です。
まとめ:手取り25万円ならば結婚後は共働きで家計の安定を図ろう
勤労世帯の平均的な生活費は、一人暮らしは約17万円、家族がいる場合は約30万円です。手取り給与が25万円の場合、一人暮らしなら余裕のある生活ができるが家族ができると生活が厳しくなります。
収入の大幅アップが困難であれば、結婚後は共働きを選択することがおすすめです。家計の安定やマイホーム購入、教育費・老後資金の準備に効果的です。
当メディアの運営会社であるシュアーイノベーションは、マネーコーチというオンライン家計相談サービスを提供しています。マネーコーチは、経験豊富なFPが無料で家計を診断し、あなただけのライフプランニングをサポートします。
お金に関する悩みについて相談したい方は、マネーコーチをぜひご利用ください。